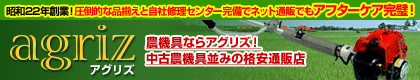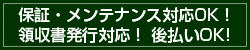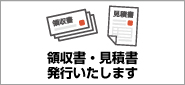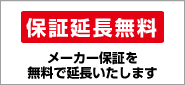農業で使用する農POには様々な厚みのものが存在しています。 基本的に良く利用されるのは0.02ミリ~0.15ミリの農POで、厚みによって耐久性や金額が大きく違ってきます。 薄い農POは非常に軽いため、農ビニールと比べてハウスの展張に使いやすいと言う特徴があります。農ビニールと比べると重さは約三分の二程度ですから、小型のハウスであれば一人でも農POを張ることが可能でしょう。 厚手の農POはやはり耐久性が非常に強いため、一度張ってしまえば最長で5年程度一切張り替えを行う必要が無いと言われています。長期間作物を育てる場合には厚手の農POが向いているでしょう。 農POの場合、少々厚くなっても光の透過性を維持できるため、農ビニールのように透過性が悪くなって毎年張替えを行う必要もないのもメリットです。これは薄手でも厚手でも透過性の劣化が緩やかなので、ハウスだけではなくトンネルなどにも利用しやすいのではないでしょうか。 もちろんデメリットも存在しており、農POは擦れに弱いため擦れの恐れがある場所に薄手の農POを使用してしまうとすぐに破れてしまうとうことも考えられます。擦れの恐れがある場所には厚手の農POか擦れに強い農ビニールを使用したほうが作物を育てるには向いていると言えるでしょう。 |
 |
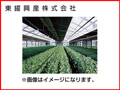 |
農POに関するページはこちら! |
 |
硫黄は農作業には欠かせない成分で、硫黄を使った燻煙や農薬自体に硫黄が含まれているものが非常に多く使用されています。 農ビニールであれば硫黄による劣化はそれほど問題ないのですが、農POに関しては硫黄を含む農薬散布などで一気に劣化が進んでしまう恐れがあります。 劣化した農POは非常に脆くなってしまう性質があり、簡単に穴が開いたり、強風で破けやすくなってしまいます。破けやすくなる以外にも、変色や透過性が著しく落ちてしまうことも考えられますから、そうなってしまうとせっかく張った農POを張替えしなければいけないと言う事態になってしまいます。 基本的に硫黄を使用する農場では農POの使用は向いていないといえますから、そういった場所では農POではなく農ビニールを使用すると問題が起きにくくなります。 注意しなければいけないのは、内部で硫黄を使用するだけでなく、外部から飛散してくる硫黄での劣化でしょう。 大きな農場になればここでは硫黄を使用していなくても、隣で硫黄入りの農薬を散布することも考えられますので、それによって農POが劣化してしまうケースも多々見受けられます。 適材適所とおい言葉があるように、農POを使用する場合には硫黄を使用しない場所での利用が望ましいと言えます。 |
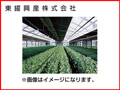 |
農POに関するページはこちら! |
農POの熱貫流率というのは、簡単に言えば保温性のことです。 熱貫流率の値が小さければ小さいほど、ハウス内の保温力は高まりますから、農POを選ぶ際にもこの熱貫流率というものは非常に重要になっていきます。通常ハウス内の熱は放熱により徐々に逃げていくわけですが、この放熱を出来るだけ最小限に抑えることでハウス内の温度は一定に保たれるわけです。 特に冬場のハウス内は、外気温が下がることにより内部の温度もどんどん低下していきますので、もちろん農作物にも大きな影響を与えてしまいます。特に温度変化に敏感な作物の場合、ハウス内の温度が下がることで生育に影響が出たり、酷い場合には枯れてしまうという恐れもあるわけです。 そうならないためにも農POを選ぶ際には熱貫流率の良いものを選ぶ必要があると言えます。数年前までは農POの熱貫流率はそれほど高くなかったため、農ビニールを使用したほうがハウス内の保温力は高く保つことが出来ていました。しかし近年では農POの技術革新が進み、農ビニール並みの保温力を持つ商品も多数販売されています。 薄くて軽く安価でしかも保温力の強い農POというものもありますので、それを使用すればハウスにかかるコストも軽減でき、ハウス内部の保温力も維持することが可能になるでしょう。 |
 |
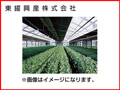 |
農POに関するページはこちら! |